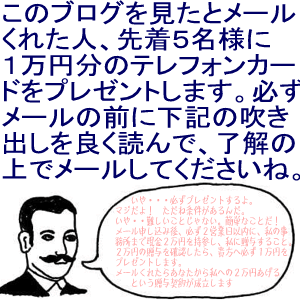純国産OS
私の曖昧な記憶によると、アメリカでウインドウズやマックOS(マッキントッシュ)という、グラフィカルユーザインタフェース (GUI) のオペレーションシステムが産声をあげた頃、ここ日本に於いても画期的なGUIによるOS(基本ソフト)が作られました。
それは「トロン」と呼ばれるOSです。
その基本構造として、後にインターネットブラウズ等で使われる事となる「ハイパーリンク」を操作の基本として利用する先進的な構造であったり、OSとして漢字を扱えるだけでなく、OSとしての安定性も当時の「ウインドウズ」や「マッキントッシュ」などと比べると、比較にならないものだったのですが・・・・・残念なことに、「トロン」は日本においてさえ普及することはありませんでした。
では、何故「トロン」は、普及しなかったのでしょうか?
色々な説があるのですが、一番大きな原因は「トロン」の優秀さを恐れた「アメリカ様」の外圧に、当時の日本政府が屈したため・・であったと記憶しています。
トロンの数奇な運命
「トロン」は、その後「ビーライトV」や「超漢字」という商品名で、パーソナルコンピューター用のオペレーションシステムとしても販売されたのですが・・如何せんその時には既に「ウインドウズ」が市場を席捲しており、「ビーライトV」や「超漢字」用に新たなソフトやドライバーが作られることもなく、周辺機器も対応することはありませんでした。
コンピュータは、「ソフト無ければ只の箱」・・・これはオペレーションシステムにも言える事で、そのOSで動くソフトや周辺機器が無ければ、どんなに基本が優れていても、只の器にすぎず、結局「トロン」は、パーソナルコンピュータの世界では一部のマニア以外には見向きもされませんでした。
つまり・・何が言いたいのか?
世に広まっていたり、多くの人が利用しているものが、必ずしも「正しいもの」や「優れているもの」では無く、逆にある一定の情報操作であったり、力関係で実は不便を強いられていることがあるということなんです。
こういう事って、知らないでも困らないかもしれませんが、世の中の仕組みとして、こういう事実があるのだと言うことを知っておくことで、ある事柄で自分が本当に求めるべきものが何んであるのかを、それらを知らない人よりも正しく判断できるのではないのかと思うのです。
もっとも「知らぬが仏」とも言えますが、私はどうせなら知っていたい。
その違いは小さいけれども、「知っている」・・「知らない」・・事で、その人にもたらすメリットであったり、考え方に多大な違いをもたらすのではないか?
見かけで騙されない為に必要なことだと思う今日この頃。
これはテレビやネットなどで広告をしているところが、必ずしも善人ではないという事実や、垂れ流される情報が一方的で、必ずしも正確なものでは無いということにも繋がっています。
会社の設立
会社の設立を業として行えるのは「司法書士」か「弁護士」しかできない。
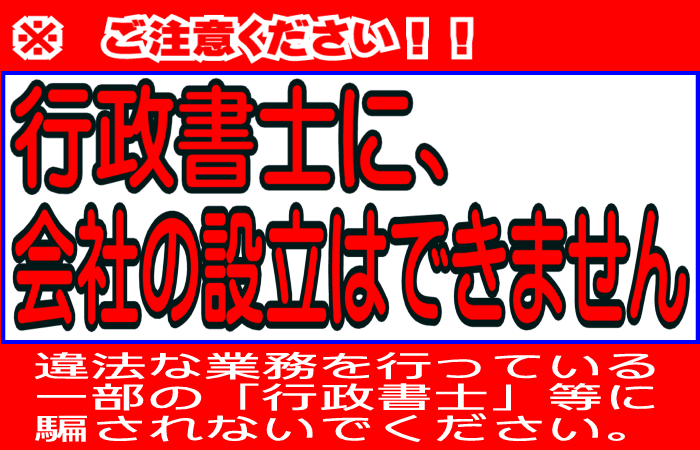
※誤解のないように言っておきますが、もの凄く優秀な行政書士の先生も多くいらっしゃいます。別に行政書士全体が悪いといっているのではなく、あくまでも一部の違法な業務を行う行政書士に気をつけてね・・という意味です。
しかし、
特にインターネットの世界で「会社 設立」と検索をすると、
この二つの資格者・・まぁ、「弁護士」はできるとはいえ、元々会社の設立を仕事としていないので、当然だが検索結果に表示されない。
なので、「弁護士」が「会社 設立」で検索されないのは、当然といえよう。
問題なのは、本来は商業登記の専門家である「司法書士」が、「会社 設立」と検索しても検索結果に表示されないことだろう。
これは、会社法の施行により、単純に昔に比べて会社の設立が簡単になった・・・という側面も大きいが、それ以上に、司法書士が、ボサ~ッとしていた結果とも言え、自業自得な面もある。
しかし、厳密に法律を精査するまでもなく、会社の設立を仕事とできるのは、弁護士を除けば司法書士しかいないのだが、ネットの世界では完全につまはじきにされている不思議な実態・・いったいどうなってんだ?
この先の道
余談ですが・・それでは「トロン」は死んでしまったのでしょうか?
実は「トロン」は死んだりしませんでした。
「トロン」の安定性は、車のOSであったり、白物家電のOSという、何よりも安定性を求められる部分に、人知れず利用されるようになりました。
考えてもみてください。
ウインドウズ8になっても、たまに突然コンピュータが操作できなくなり、勝手に再起動したりする不安定なOSが、車に積まれて誤作動を起こしたら・・・考えただけで背筋が寒くなりませんか?
そして「トロン」は・・・ウィンドウズと歴史的「和解」 共同研究で提携・・・という道を歩みます。
まぁ、個人的な話をすると、今更大きな事ができる訳でもありませんが・・・
せめて・・どこにでもある雑草として
人知れず、家族の生活を支え、依頼者を支え続ける・・・
そんな「トロン」に私はなりたい。
ご提案
日司連に言いたい。
実質的な話・・・残念ながら、ここまで会社の登記が他業種に浸食されている現状・・・
この訳のわからない状況を打開する気が無いのなら
もう
商業登記を他業種に解放しちゃえ
そのかわり、得るものをしっかりと得て、国民のために司法書士が有益であることをしっかりと示すことに方向を転換すべき時期にきているのではないだろうか?
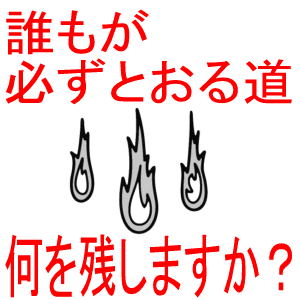 「行きはよいよい、帰りは怖い」
「行きはよいよい、帰りは怖い」
 「契約について考えるシリーズ 最終話」です。
「契約について考えるシリーズ 最終話」です。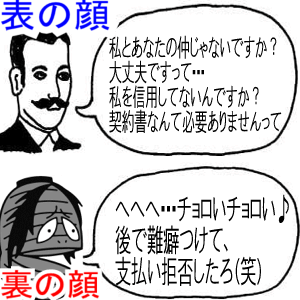
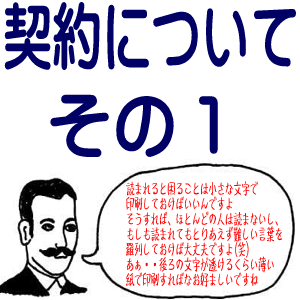 今日は「契約」について考えてみます。
今日は「契約」について考えてみます。