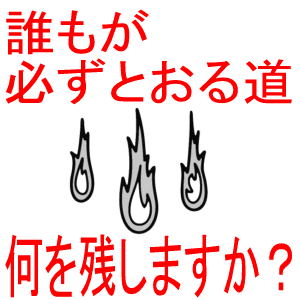 「行きはよいよい、帰りは怖い」
「行きはよいよい、帰りは怖い」
どこかで聞いた言葉
言うまでもなく、童謡「通りゃんせ」の一説です。
この「通りゃんせ」という童謡の歌詞については様々な解釈があるようですね。
今日は童謡の解釈とはちょっと違う視点から「行きはよいよい帰りは怖い」を考えてみたいと思います
・・って・・
それほど大げさな話でもないですが・・(^^;)
人生
人は生まれた瞬間から、死に向かって進みます。
子どもの頃は、永遠のようにも感じた世界も、年齢を重ねるほどに何時かは人生を折り返し、そのうち生まれる前の世界へ帰って行くとするならば・・・
まぁ、難しいことはいいか・・・
はっきりとしていることは、
この人生には終わりがある
ということだ。
人生の終わりを考える
多くの場合、あれを始めようと決めることは比較的やさしいことだが、それを何時どう言う形で終わらすのか・・終わってしまうのか・・ということは中々に難しい。
思うに・・はじめる時には色々と道しるべがあるのだが、終わるときには道しるべって無いことが多いな・・・
死ぬことの準備
縁起でも無い
とお叱りをうけるかもしれないが、
避けることのできない「死」とは、誰もが何時か向き合う時が来るようです。
まぁ、それは仕方が無いとしか言いようが無い。
何ができる
自分の寿命があと何日あるのか?
これも誰にもわからない。
50年後かもしれないし、1分後かもしれない。
今は残せるものが無い人も、できることは?
備えよう
先日Xさんからこんな相談がありました。
相談の前提としての全体構図
相談者(X)の、
お母さん(A)は、H1年2月3日に亡くなりました。
相談者(X)は、H2年9月9日に結婚し、実家をでた。
お父さん(B)は、H5年6月7日に、後妻(C)と結婚した。
お父さん(B)は、H17年8月9日に亡くなりました。
お父さん(B)は、自宅(甲土地・乙建物)を所有していました。
お父さん(B)の遺言はありませんでした。
お父さん(B)の遺産についての協議は特に行われなかった。
後妻(C)が、H24年2月7日に、亡くなりました。
後妻(C)の遺言はありませんでした。
後妻(C)が亡くなったこともあり、お父さん(B)の遺産を整理する中で、甲土地と乙建物の不動産の謄本(全部事項証明書)を取得したところ、
甲土地・乙建物は、
平成23年10月に、なぜか法定相続で登記がされていたそうです。
つまり、甲土地・乙建物を、
相談者(X)さん 2分の1
後妻(C)さん 2分の1
で相続登記がされたということです。
相談者(X)と、後妻(C)は養子縁組をしていません。
つまり、相談者(X)と、後妻(C)は、法律上は赤の他人。
相談者(X)は、後妻(C)の事はほとんど何も知らない。
相談の内容
相談者(X)は、
「甲土地と乙建物は、現在誰も住んでいない。 市から、甲土地と乙建物の、固定資産税を支払えと言われているので、甲土地と乙建物を処分(売却)したいと考えているが、後妻(C)の共有持分の取扱はどうなうのかが知りたい」
というのが相談の内容です。
困った
このケース・・・実は最悪です。
相談者(X)は、後妻(C)の相続人ではありませんので、後妻(C)の相続人を調査することができません。
勿論、私たち司法書士にしても、後妻(C)の相続人でない相談者(X)からの依頼では、後妻(C)の戸籍を取得することができません。
その結果・・・
後妻(C)について、相続人の調査ができませんので、それに続く相続登記もできません。
相続登記が出来ない以上、甲土地・乙建物を処分(売却)することができません。
まぁ、何をするにしても、後妻(C)の相続人の確定は避けてとおれない道です。
苦肉の策
・・・と言うわけでも無いですが・・・
実は、この場合でも相談者(X)なら、後妻(C)の相続人の調査のために、後妻(X)の戸籍を収集する方法があります(勿論法律的に何の問題もない方法です)。
ただ・・・
やっぱり・・
ちょっとやり方が
トリッキー過ぎて、
その方法を公にはしません・・・(>_<)・・・。
相続
司法書士をしていると、こういう相続に関する問題って色々と見聞きします。
そういう中で、やはり大切なことは、後に残された人が困らないようにしておくことです。
つまり、
生きている間に色々と持っている財産・・・
れら財産を
「自分が亡くなった後に、どのように処分するのか?」を
しっかりと、考えておくべきです。
そして、できれば「遺言」を作成しておき、自分が亡くなった後に大切な家族が困らないようにしておくことは、とても大切なことだと思います。
相続のご相談は、お近くの弁護士か司法書士までお気軽にお問い合せください。
通りゃんせ 通りゃんせ
ここはどこの 細道じゃ
天神さまの 細道じゃ
ちっと通して 下しゃんせ
御用のないもの 通しゃせぬ
この子の七つの お祝いに
お札を納めに まいります
行きはよいよい 帰りはこわい
こわいながらも
通りゃんせ 通りゃんせ

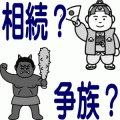
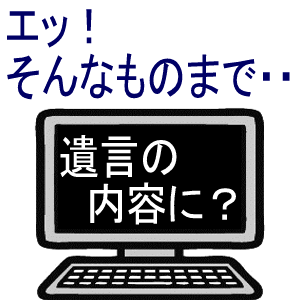
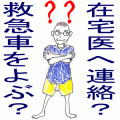

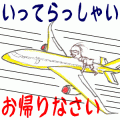

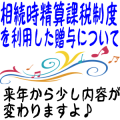

コメントを残す