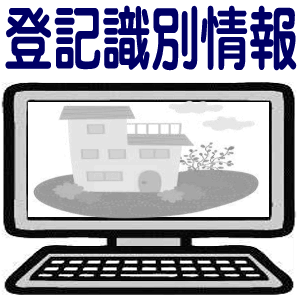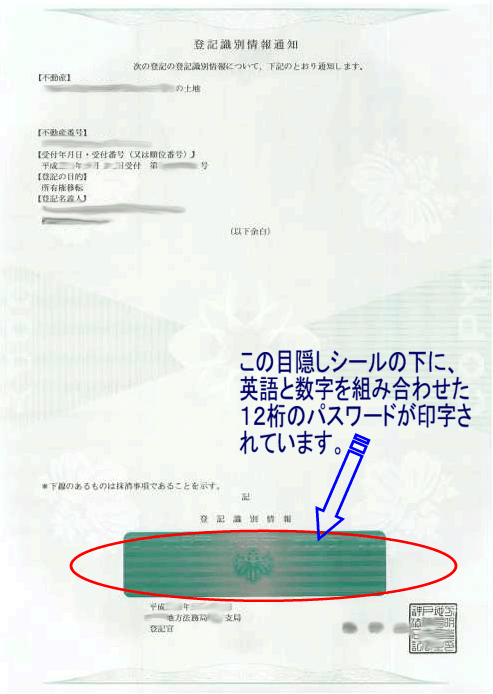あまり無いと言えばないのですが、2年に一度程度・・・
あまり無いと言えばないのですが、2年に一度程度・・・
「クレジットカードで支払えますか?」
と言われることがあります。
今までは、カード決済はお断りしていたのですが、ここ最近私のような中小零細な事業者でも簡単にカード決済をすることができる便利な道具がでてきました。
そこで、カード決済ができるように「Square」を利用したモバイルカード決済を導入しました。
自分のカードを使ってテスト決済をしてみましたが・・・
「簡単」に決済することができました。
実際の運用にあたり、もう少しテストを行う予定ですが、中々便利なものだと思います。
そこで、「Square」のメリット・デメリットを考えてみました。
- 「Square」の利点
- スマホか、タブレットがあれば簡単に決済ができる
- スマホ等につけるリーダーが無料である
- 依頼者様の支払い方法に幅ができる
- 使い方が簡単である
- 「Square」のデメリット
- 「一括払い」しか選択できない
- 決済手数料が3.25%必要
- カード決済特有の注意点がある(下記参照)
- この形式の決済方法がもっと認知されなければ、場合によっては怪しく映るか?
なお、カード決済を行う場合には、現金決済と違う注意点があります。
カード決算の注意点について
- 正規のカードの仕様や特徴を理解して、対象のカードが本物であるかどうかを見分けられるようにしておく必要がある。
- カードの有効期限の確認すること。
- カードにサインがない場合には、写真付きの身分証明書を提示していただき、カードの氏名と身分証明書の氏名が同じかどうかを確認すること。
- カードに問題が見つかった場合の対処方法を予め決めておく(不正使用が疑われる取引の処理方法や問題発生時の連絡先などをあらかじめ決めておく)。
- カード保有者のいかなる情報(例:クレジットカード番号)を、どのような形であれ(例:書面上、インターネット上、ソフトウェア内など)保存するようなことがないように注意すること。
まぁ・・・と・・言う訳で・・・
当事務所では、カード決済が利用できるようになりました。
あとは、カード決済してもらうための、お仕事があれば・・・(T_T)
※ なお、業務の内容によっては、カード決済が利用できない業務もございます。
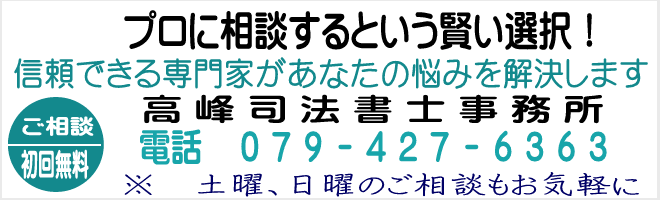
相談のご予約メールフォームはこちら
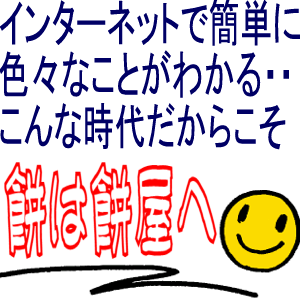
 早いもので、今年も6月となりました。
早いもので、今年も6月となりました。