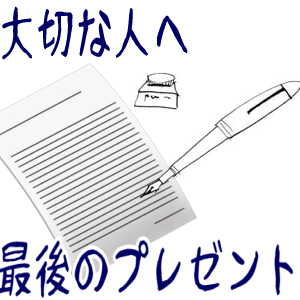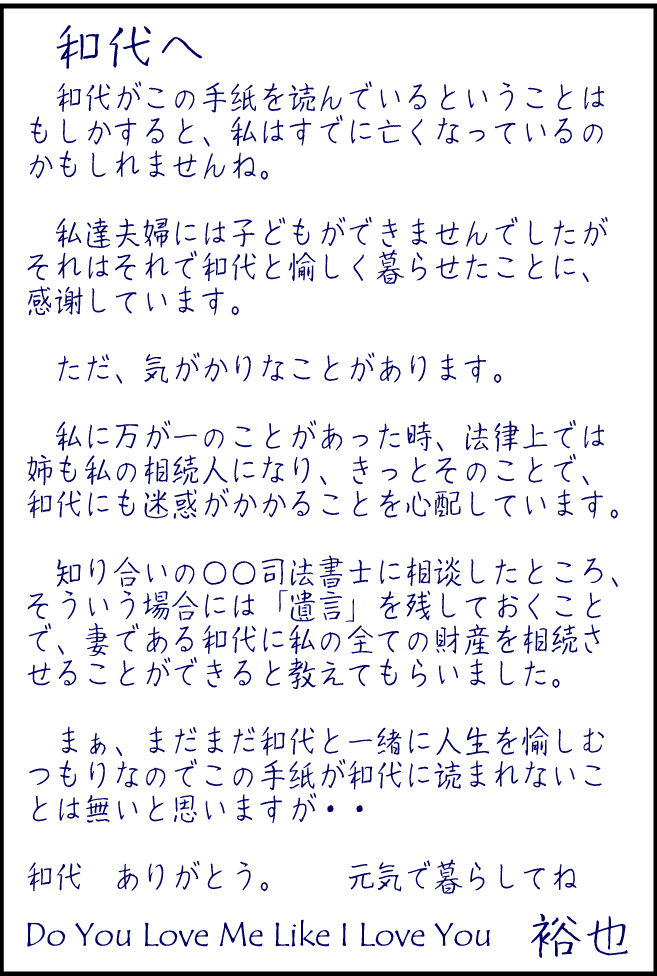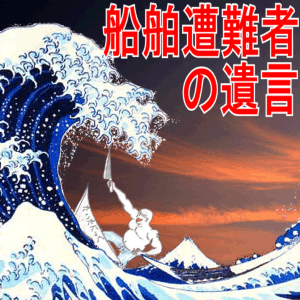
船舶遭難者の遺言
もしも乗船している船が遭難したり、沈没の危機にあるような場合に行える遺言です。
どんな場合に行えるのか?
遭難している船舶中にあって死亡の危急に迫った人が行えます。
※ ここでいう「遭難」とは、船舶自体が滅失するとか、又は重大な毀損の危険があることをいい、その危険は急迫であることが必要となります。
※ 船舶の遭難という、かなり特殊な事情のために、他の特別方式による遺言に比べると、かなり要件が簡略化されています。
やり方
-
証人2名以上の立会いが必要(注1・注2)
(注1)・・証人には欠格事由(未成年者・被後見人・被保佐人・推定相続人(及びその配偶者)・受遺者(及びその配偶者)・直系の血族)があります。
(注2)・・事務員とは、「航海士」「機関長」「機関士」「船舶通信士及び命令の定めるその他の海員」をいいます -
遺言者が、口頭で遺言をすること(注3)
(注3)・・この方式の場合には、口頭遺言が許されます。
-
証人が遺言の趣旨を筆記し、これに署名捺印をすること(注4)
(注4)・・筆記は、遺言者の面前で行う必要はありません。また、筆記を遺言者と証人に読み聞かせることも必要ありません。また、これらのうち署名捺印ができない人がいる場合には、立会人または証人がその事由を付記しておく必要があります(つまり、署名捺印ができない人でも証人となりうるということです)。
確認
民法第979条の船舶遭難者の遺言については、家庭裁判所での確認の審判が必要ですが、その請求は家庭裁判所への確認を求めうる状況となってから「遅滞なく」と定められており、死亡危急時の遺言のように20日以内という限定はありません。
その他の注意点
船舶遭難者の遺言をした人が、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、船舶遭難者の遺言は、効力を生じません。
関連する記事
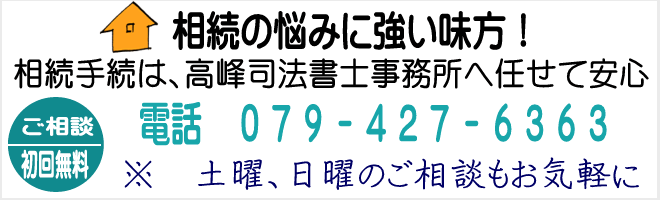
こちらからメールフォームをご利用ください
ところで
英国のタイタニック号や、韓国のセウォル号の事故を考えるに・・
考えれば考えるほどに海難事故で船が沈没してしまうような事故を起こしたときの恐怖は凄いものがあるでしょうね。
仕事などで、どこかホテルで宿泊するような場合には、必ず非難通路や非難の方法を確認するようにしていますが、外洋を走る船の上では救命ボートに乗り移るより他に助かる道がなさそうです。
しかし、船自体が傾きだしたときに、そもそも救命ボートまでたどり着けるのかを考えると夜も眠ることができません・・・
あっ・・・そもそも外洋を走る豪華客船に乗るためのお金を貯めなければいけませんね。
なんだ・・全然心配する必要ないじゃないか(大笑)
まぁ、その時が来たらあらためて心配することにしますが、沈みゆく船で遺言をするくらいなら、船で旅をするその前に「自筆証書遺言」か、「公正証書遺言」を作成しておくことを忘れずにお願いします。
それにしても、今年も残り約4分の1となりました。
ふと・・今の自分と、一年前の自分とを比べてみて、何か進歩したのだろうかと考えたのですが・・・
一年前には出来なかったことが、今では何とかこなせるようになったものもあるのですが、その反面出来なくなったこともあることに気がつきます。
まぁ、全てを吸収していくことは不可能でしょうから、いらないものはそぎ落としていく事も必要なことなのでしょうが、トータルでは出来ることが増えた・・はず・・(^^;)
色々な環境や状況が変化する中で、仮に一年前と同じだとしても、それは後退していることになるのではないでしょうか?
さてはて、1年後に、今の自分は「駄目じゃん」と思えるように、一所懸命あえいで、実りある時を過ごしましょう。
あぁ・・そういえば・・この一年でそぎ落ちてしまったものが、少なくとも大筋で幹の部分じゃないことを祈ります(笑)
それでは、良い一年を・・
 昨今、一週間から1ヶ月程度の豪華な船旅を優雅に楽しむという旅行が人気あるらしいですね。
昨今、一週間から1ヶ月程度の豪華な船旅を優雅に楽しむという旅行が人気あるらしいですね。 最近のニュースで、ヒトスジシマカを媒体とする「デング熱」や、マダニを媒体とする「重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルス)」やら、何やら聞き慣れない伝染病の症例が日本各地で確認されています。
最近のニュースで、ヒトスジシマカを媒体とする「デング熱」や、マダニを媒体とする「重症熱性血小板減少症候群(SFTSウイルス)」やら、何やら聞き慣れない伝染病の症例が日本各地で確認されています。 遺言の方法として、通常は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」若しくは「秘密証書遺言」の三種類遺言を行うことになりますが、これとは別に「特別の方式」による遺言というものが4種類ありまして、そのどれもができれば利用する機会がない方がよいものですが、万が一のときにはそういう遺言もできるということを知っておいて損はないと思います。
遺言の方法として、通常は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」若しくは「秘密証書遺言」の三種類遺言を行うことになりますが、これとは別に「特別の方式」による遺言というものが4種類ありまして、そのどれもができれば利用する機会がない方がよいものですが、万が一のときにはそういう遺言もできるということを知っておいて損はないと思います。