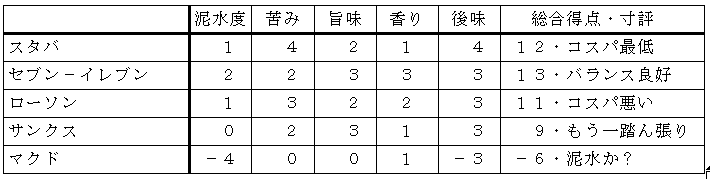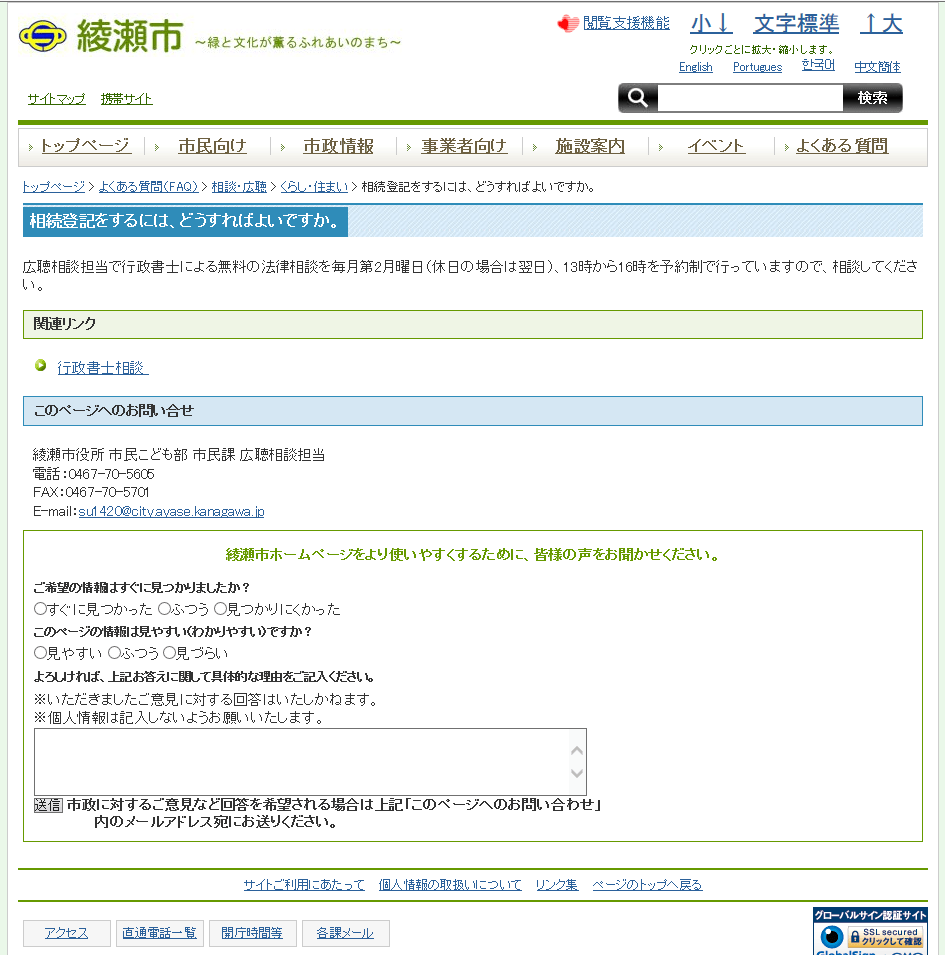今日は、デジタルカメラと登記制度についてです。
今日は、デジタルカメラと登記制度についてです。
いまや、カメラといえば「デジタルカメラ」になりました。
たしかカシオが一番最初に売り出したと記憶していますが、デジカメの進歩とともにフィルム式のカメラから主役の地位を奪っちゃいました。
まぁ、何といっても便利ですからね。
デジカメの一番のメリットは現像しなくても、その場で確認して何度でも取り直すことができることですが、これがデメリットにもなっているのではないかと、少し考えるところです。
フイルム式カメラのメリット
フイルム式カメラの場合、一枚一枚を丁寧に撮影していました。
理由は、撮影できる枚数に限りがあり、フィルムを購入するにも、現像するのにもお金がかかる。
おのずと、
この一枚にかける執念といいましょうか?
失敗できないという緊張感といいましょうか?
シャッターを押すと100円程度は必要となるので、一枚取るたびに、出来上がりを想像しながら、構図を考え光を考えながら撮影していました。
これに比べ、デジカメはメモリーカードの許す限りいくらでも撮影できますし、シャッターを押すという行為に、実質的な費用が発生しないのと、取ったその場ですぐに確認できちゃうので,一枚一枚の出来をあまり意識する必要がなくなりました。
それこそ「下手な鉄砲数うちゃ当たる」の言葉のままに、とりあえず撮影ができてしまいますので、私のように本来邪魔くさがりの人間の場合には、一枚一枚を考えて撮るという作業をしなくなってしまい、結果フィルムカメラで撮った写真と比べるとデジカメの絵は何かが足りないと感じてしまうこともありました。
何が足りないのか? と書きながらも,実は未だに上達しないカメラの腕前への言い訳のような気もしますが・・・(笑)
まぁ、そうは言うもののデジカメなら撮影した後も簡単に加工もできますし、ネットで共有したりと色々と新しい楽しみ方もありますから、今となってはフイルムカメラに戻りたいとも思いませんが・・・
なお、フイルム式カメラのメリットとして、証拠能力の高さがあると思います。
デジタルカメラは、後でパソコンで自由に修正ができます。
デジタルデーターは、あまりにも簡単に色々な修正ができるので、アナログな写真と比較すれば、その証拠能力に違いがあるのではないでしょうか?
勿論、フイルム式カメラで撮影された写真も、一旦スキャナーなどでパソコンに取り込んでしまえば、自由に修正できますが、少なくとも素人では、フイルム自体への細工は難しい。
後々、争いになるような場合には、デジカメでは無く、フィルム式のカメラで撮影していた方がよいかもしれません。
価値の創造
デジカメの発明とその進化により、携帯電話にさえデジカメがついている昨今、写真を撮るという同じ結果に至るプロセスが大きく変わり、写真に新しい価値が創造され、その結果、世界中の何億という人が手軽にカメラマンとして写真を楽しむ時代になりました。
プロ
世界には、何億人というカメラマンがいますが、それでもプロカメラマンと呼ばれる人種の撮った写真と、私のようなど素人が取った写真とは、明らかに超えられない違いがあるんですよね。
同じ機材、同じシュチュエーション、同じモデルを使っても、プロとアマの違いはわかります。
プロとアマの違いは、「その一枚にかける」気持ちの差かもしれません・・・その差は小さいのかもしれませんが、超えることが出来ない差・・・その差を取れるプロはやっぱり凄いと思います。
登記の電子情報化
登記の世界も、紙から電子情報へと変化し、「登記」という同じ結果に至るプロセスが大きく変わりましたが、デジカメでの写真撮影と違い、登記を失敗することは許されません。
登記業務は、とても細かいルールや約束事があり、それは登記が電子情報化されたことによって、より複雑化しています。
私たち司法書士は登記の唯一のプロとして、フイルム式カメラのシャッターを切る緊張感を持って向き合い、依頼者から「プロは凄い」と言われる仕事を行う必要があります。
タイムマシン
今日のこの瞬間を記録して未来に送る・・・もしかするとカメラって一番簡単なタイムマシンなのかもしれませんね。
そして、登記制度も、登記を見れば、その不動産の、そして会社の歴史を綴り、未来へとつなげるタイムマシンなのかもしれません。
相続の登記、所有権の移転、抵当権の抹消、抵当権の設定・・会社の設立、役員の変更、本店の移転など、登記に関する事はお近くの司法書士、若しくは、当事務所までご相談ください。
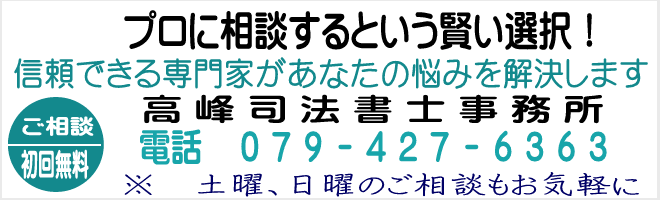
相談のご予約メールフォームはこちら
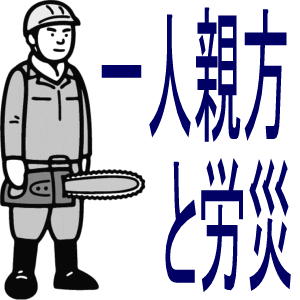
 「契約について考えるシリーズ 最終話」です。
「契約について考えるシリーズ 最終話」です。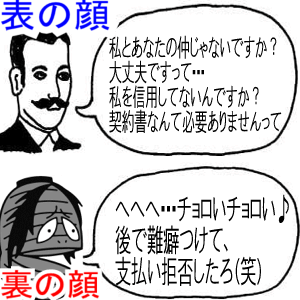
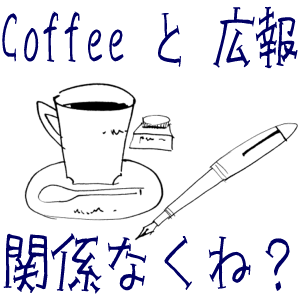 最近どうしても気になっていることがありまして・・・
最近どうしても気になっていることがありまして・・・