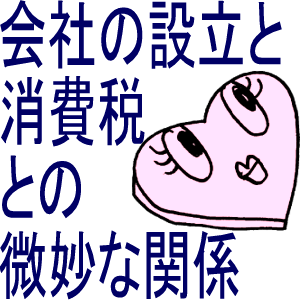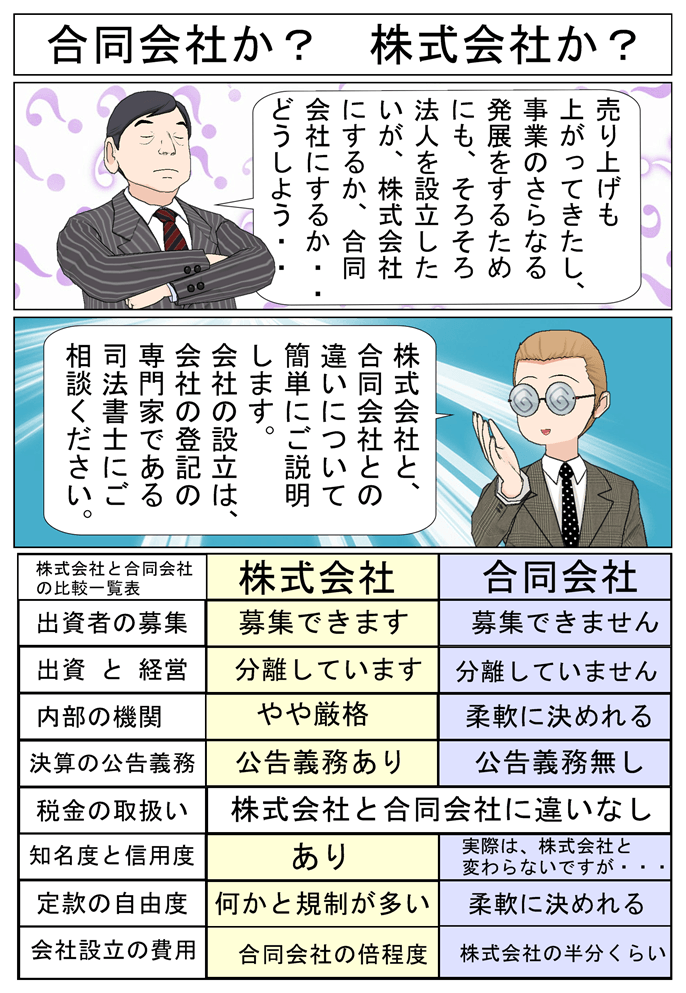部屋の片隅に、「緊急持出しバック」が置いてあります。
部屋の片隅に、「緊急持出しバック」が置いてあります。
バックの中身は、「包帯」、「懐中電灯」、「電池」、「絆創膏」、「紐」、「マッチ」、「ライター」、「軍手」、「下着」、「タオル」、「テッシュ」、「小銭」、「塩」、「飴」、「歯ブラシ」、「3年飲める水」、「カンパン」・・等々
地震とかの自然災害とかが起こった時に、最低限持ち出せば、便利かな?・・と思う物をバックに入れて準備しているものです。
この「緊急持出しバック」を置きだしたのは・・
「阪神淡路大震災」がきっかけで、2年に一回くらい中身の確認のと入れ替えをしています。
ところで・・・
兵庫県加古川市で、自分の事務所を開業し司法書士として独立ししてから早19年が過ぎました。
私が司法書士として独立したのは、「阪神淡路大震災」が発生した平成7年です。
震災当時、神戸市兵庫区にある司法書士事務所で働かせて頂いており、その事務所自身も建物こそ無事でしたが、事務所の備品が散乱し、それはそれは目もあてることが出来ない状況でした。
その事務所の周りでも道路がうねり、道路が陥没したり、近くの新築のマンションに亀裂がはいったり、建物自体が倒壊していたり、震災後の火事で一区画が焼失していたりと、「阪神淡路大震災」による多大な被害を目の当たりにし、自然の驚異と人の無力さを感じましたが、その無力感と同時に、多くの被災者が少しづつ前に進もうとする力強さも身近に感じていました。
また、当時の司法書士達も多く被災しましたが、多くの司法書士が困っている人達のためにいち早く「相談会」を開催するなどの活動を、また、特に当時働いていた事務所の先生が、自分の事務所の惨状を顧みず、被災した市民や、被災した司法書士のために走り周る姿を身近に見ました。
いつかは独立して・・とのんびりと構えていましたが・・・この阪神淡路大震災は、一人の司法書士として何ができるのかを考えるきっかけとなりました。
一人前の司法書士として地域に根付き、困っている人に司法書士としてできることは何か?
今のその答えを探すべく、日々色々な人に助けて頂きながら働かせてもらっています。
この「緊急持ちだしバック」を見ると、兵庫県加古川で開業した当時の気持ちを思いだします。
一人の司法書士として、地域の皆さまに愛されるように頑張らないと・・・
・・・話が脱線しました・・・m(_ _)m
一秒先に何が起こるかは誰にもわかりませんが、少しでもそれに備える準備は誰にでもできることです。
「緊急持ちだしバック」・・皆さまも是非ご準備くださいね。
 早いもので、今年も6月となりました。
早いもので、今年も6月となりました。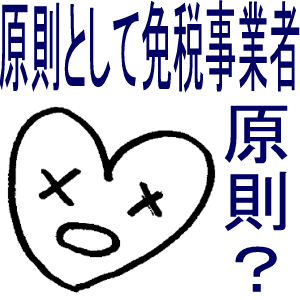 昨日のお話(
昨日のお話(