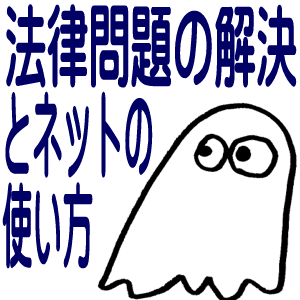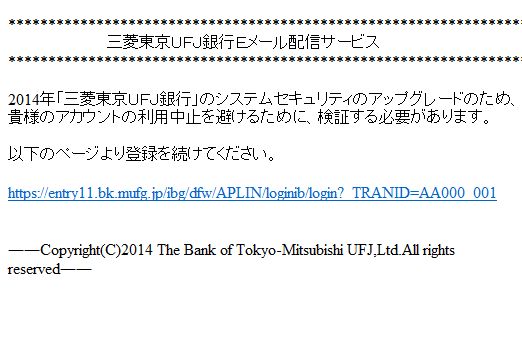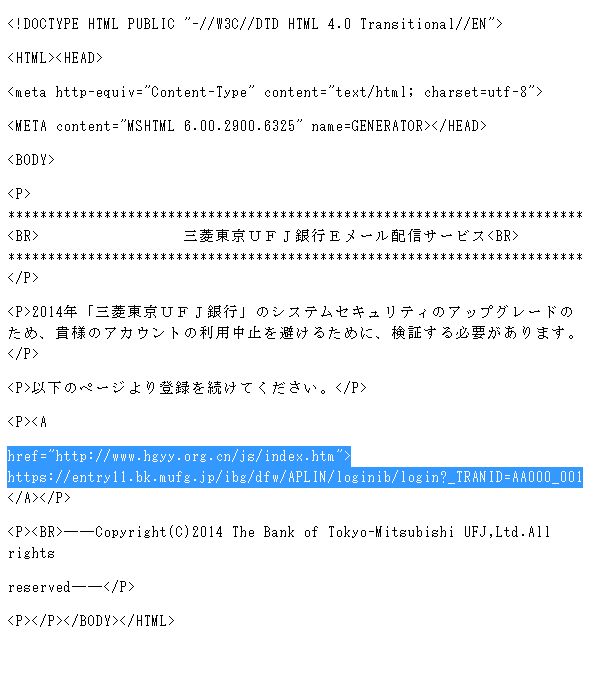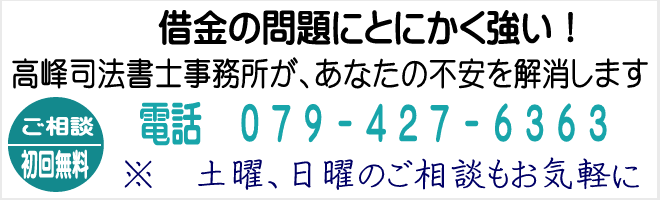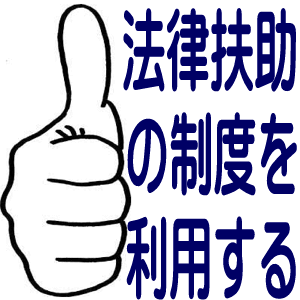
「債務整理などを司法書士に依頼しても、司法書士への費用(報酬)が必要ない?」・・そんなことあるのでしょうか?
※ はい。以下の条件にあてはまる人は,司法書士や弁護士に債務整理などを依頼しても,司法書士や弁護士の報酬等の費用が必要ない場合があります。
※ 法律扶助制度が適用されるのは、債務整理のみ・・と言うことではありません。
法律扶助制度について
法律扶助制度とは・・律相談の結果、弁護士の費用や、司法書士の費用について、代理援助や書類作成援助を行い、それらの費用を一旦国が立て替えて弁護士や司法書士に支払う制度です。
法律扶助の利用の3っの要件
- 収入等が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の主旨に適すること
生活保護を受給されている方へ
- 依頼時に生活保護を受給中の人,若しくは,これから受給しようとしている人
- 債務整理の処理が終了した時点でも生活保護を受給されている方
上記(1)で,生活保護を受給中の人は,司法書士費用や弁護士費用を国が立て替えてくれます(これを「法律扶助」といいます)。
但し・・・
国が一旦「立て替える」と言うことなので,本来は国が立て替えた金額を,後ほど国に返済(これを「償還」と言います)しなければなりません。
しかし・・・
上記で(2)に該当する場合には,国が立て替えた司法書士報酬等の償還を免除申請することで、よほどのことが無い限りは償還を免除してくれます。
と言うことで、
もしも
「生活保護を受給する予定」
「生活保護を受給中」
であるのなら,債務整理の費用を心配する必要はありません。
生活保護を受給していない・又は受給する予定も無いけれども、法律扶助の制度を利用できますか?
大丈夫です。
この場合でも,国が司法書士費用を立て替えてくれる場合があります。
どんな場合かと言いますと、上記法律扶助制度が利用できる三つの要件の(1)にある「収入等が一定額以下であること」に該当する場合です。
具体例
| 家族の構成人数 | 収 入 |
|---|---|
| 一人暮らし | 18万2000円以下(賞与を含み20万200円以下) |
| 2名家族 | 25万1000円以下(賞与を含み27万6100円以下) |
| 3名家族 | 27万2000円以下(賞与を含み29万9200円以下) |
| 4名家族 | 29万9000円以下(賞与を含み32万8900円以下) |
「え~っ・・・立て替えてくれても償還しなければいけないんでしょ?」
はい! そのとおりです(^^;)。
しかし、
下記に記載されている通常の請求する費用に比べると,約半額くらいですみますので,法律扶助を利用できる場合は積極的に利用してください。
どんな人が「法律扶助」を利用できるのか
- 収入等が一定額以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の主旨に適すること
上記の三つの要件に該当する人です。
※ なお、法律扶助制度が利用できるか否かは、実際に面談して、色々とお話しを聞いてみないとわかりません。
上記に該当しない人・・すみません・・・債務の整理に必要な司法書士費用(当事務所の費用)は下記のとおりです。
※ 法律扶助の制度を利用できない司法書士事務所もあります。
※ 法律扶助のことを含めて、お気軽にお問い合せくださいね。
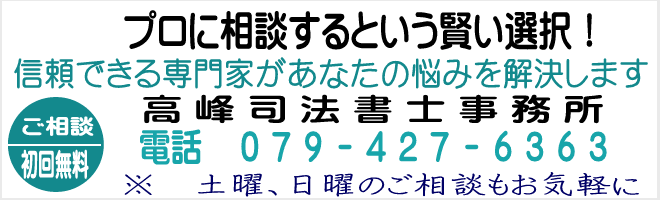
相談のご予約メールフォームはこちら